

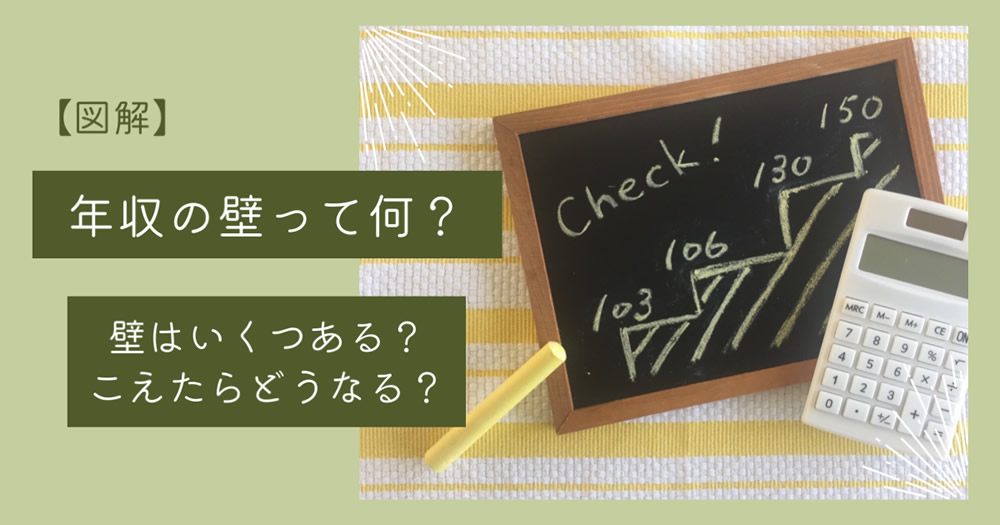
「年収の壁」という言葉をよく聞くようになりました。
年収がその「壁」の金額に達すると、税金や社会保険料の負担が発生することで、働いても手取りが減ってしまうため、壁を超えないように働き方を制御して扶養内で働く人もいます。
この「年収の壁」はいくつか種類があるのでわかりづらく、混同してしまいがちです。
年収の壁を整理して一覧でわかりやすく解説します。
目次
夫婦ともに正社員でフルタイムで働いている共働き世帯にとってはあまり関係ないかもしれませんが、夫婦のどちらかがパートやアルバイトなどで扶養内で働いている共働き世帯にとって気になるのが「年収の壁」です。
年収の壁とは、税金や社会保険などの負担に影響がある節目・ボーダーラインの年収のことです。一般的には扶養の範囲から外れることとなる年収のことを言います。
年収が壁を超える=世帯主の扶養から外れる⇒税金や社会保険料の負担が発生⇒働いても世帯の手取り年収が減る=働き損、と捉える人が多く、壁を超えないように働き方を制御して扶養内で働く人もいます。
年収の壁は、「税金に関わる壁」と「社会保険に関わる壁」の2種類あります。たくさんの金額に壁があるので複雑に思えますが、整理して一覧表にすると少しわかりやすくなります。
年収の壁を、税金にかかる壁と社会保険に関わる壁に分けるとこのようになります。
年収の壁は、たくさんの金額に壁があるので複雑に思えますが、整理して一覧表にすると少しわかりやすくなります。
年収の壁を、被扶養者(扶養に入る人)と、扶養者(扶養している人)ごとに整理すると下記のようになります。
| 被扶養者(扶養される人) | 扶養者(扶養する人) | ||||
| 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 所得税(控除) | ||
| (106万円未満) | 負担なし | 負担なし | 負担なし 扶養加入できる | ||
| 106万円の壁 (106万円超) | 負担なし | 負担なし | |||
| 110万円の壁 (110万円超) | 負担なし | ||||
| 130万円の壁 (130万円超) | 負担なし | ||||
| 150万円の壁 (150万円超) | 負担なし | ||||
| 160万円の壁 (160万円超) | |||||
| 201万円の壁 (201万円超) | |||||
*1 学生は対象外
*2 扶養から外れる(19歳以上23歳未満以外の人)
*3 扶養から外れる(19歳以上23歳未満の人)
*4 子の年収が188万円を超えると特定親族特別控除の対象外となる
上の図を見ると、税金(所得税や住民税)に関する壁なのか、社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)の壁なのかがひと目でわかります。
扶養されている人の年収が壁を超えると、扶養されていた本人の納税負担が増えるだけではなく、扶養している人(世帯主)も配偶者控除や配偶者特別控除の控除額が減ったり 控除を受けられなくなるため、税金の負担が増えることとなります。
これにより、年収が増えたはずなのに世帯の手取り年収が減ってしまうという現象が起こることがあります。
それぞれの年収の壁をこえたらどうなるのか、詳しく解説していきます。
まず、年収110万円を超えると住民税が発生することになりますが、これは厳密には自治体によって異なるので目安として考えてください。
110万円を少し超えたぐらいでは住民税負担額は小さいので、気にしている人はあまりいないかもしれません。
※所得控除等により、108.8万円までは非課税となります
※自治体によって非課税となる年収額が若干異なる場合があります
だいたいの目安として、年収110万円を超えると「均等割」が課税され、それ以上になると「所得割」も加算されます。
年収120万円なら、年間で約5500円の負担となります。(自治体によって異なります)
160万円の壁=税金の壁です。(所得税)
年収が160万円を超えると、所得税が発生します。
年収が160万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかります。
ですので、年収が160万円を超える人は、所得税・住民税をどちらも納める必要があるということになります。
所得税は、年収160万円を超えた分に税率5%で課税されます。
年収160万円なら、年間で約1000円の負担となります。
負担額だけ見るとそれほど大きくないとも言えます。
2025年の税制改正により、所得税の年収の壁が引き上げられ、もともと103万円の壁だったのが「160万円の壁」になりました。
詳しくは下記の記事でまとめています。
![[2025税制改正]年収の壁って結局どうなったの?](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/07/nensyunokabe2025kaisei-300x169.jpg)
106万円の壁=社会保険料の壁です。
勤務先の規模によって社会保険に加入しなければなりません。
年収106万円の壁は「社会保険加入の壁」なのですが、これは勤務先の規模によって該当する人・しない人がいます。
社員数51以上の企業で働いている人は、年収106万円以上になると勤務先で社会保険に加入することになります。(=これまで世帯主の扶養に入っていた人は保険料負担が0円でしたが、自分で社会保険に加入するので社会保険料の負担が増えるということになります。)
※106万円の壁(社会保険加入の年収要件)は、2026年10月までに撤廃される予定です。
※企業規模要件(従業員が51人以上)は段階的に縮小され、働く企業の規模に関わらず、社会保険へ加入するようになります。
詳しくは下記の記事にて解説しています。
![[106万円の壁撤廃]社会保険加入の壁はなくなる?年金制度改正法](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/07/nenkinkaisei_160kabe-300x169.jpg)
社会保険料は、年収の約15%程度です。
年収が106万円の場合、社会保険料は約15万円となります。
年収105万円の場合は社会保険料が0円なのに、106万円になると15万円に!
少し壁を越えただけで15万円も給与から引かれると考えると、手取り金額だけをみると社会保険料の負担は大きいと言えます。
※社会保険に自分で加入することによるメリットももちろんあります。詳しくは後述します。
130万円の壁=社会保険料の扶養の壁です。
年収が130万円を越えると被扶養者の対象から外れます。(19歳以上23歳未満の人は年収が150万円を超えると扶養から外れます。)=勤務先企業の規模に関わらず、勤務先の社会保険(または国保)へ加入となります。=扶養に入っていれば社会保険料の負担がありませんが、扶養から外れると自分で保険料を負担することになります。
年収が130万円を超えると、住民税・社会保険料が給与から天引きされることとなります。
年収131万円の場合、手取り金額は約110万円になります。
年齢19歳以上23歳未満の人が扶養に入るための年収要件が、150万円未満に引き上げられました。(2025年10月1日~)
詳しくは下記の記事でまとめています。
年収の壁は、パート・アルバイトで働く本人だけの問題ではなく、扶養している世帯主にとっても関係のある話です。=世帯全体での手取り収入に直結する問題です。
扶養している側に関係があるのが、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「特定扶養控除」「特定親族特別控除」という所得税に関わる制度です。
簡単に説明すると、これらは家族を扶養している人の所得から一定額を控除することができるもので、控除を受けると所得が少なくなるため、所得税と住民税が安くなるというものです。
扶養している人(世帯主)にとっては、扶養されている人(配偶者や扶養親族)の年収が増えることで配偶者控除や配偶者特別控除、特定扶養控除が適用されなくなると、税金負担が増えることになります。
配偶者控除と配偶者控除は、どちらも、年収が一定額以下の配偶者を扶養している人の所得税が安くなる制度です。
配偶者控除と配偶者特別控除は、対象者の要件と控除額が異なります。
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、配偶者特別控除額が減額され、1,000万円を超えると控除は0円(適用なし)になります。
| 配偶者(扶養されている人)の年収 | |||
| 年収123万円以下 | 年収123万円超 160万円以下 | 年収160万円超 201万6千円未満 | |
| 扶養している人の合計所得金額 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 38万円 | 3~36万円 |
| 950万円以下 | 26万円 | 26万円 | 2~24万円 |
| 1000万円以下 | 13万円 | 13万円 | 1~12万円 |
特定扶養控除と特定親族特別控除は、どちらも19歳以上23歳未満の扶養親族がいる人が受けられる控除です。
特定扶養控除は、子どもの年収が123万円以下でなければ親は控除を受けることができません。
特定親族特別控除は2025年の税制改正で新たに創設された控除制度で、この世代の子どもの年収が150万円以下であれば、親は特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができます。
子どもの年収が150万円を超えると、控除額は段階的に減少し、年収188万円を超えると控除額は0になります。
ですので、学生アルバイトが親の税金負担を気にしながら働く場合は、「150万円の壁」を意識することとなります。
親の年収に制限はありません。
詳しくは下記の記事にて解説しています。
パートやアルバイトの収入が「年収の壁」を超えると、新たに社会保険料や税金の負担が生じます。
このため、出勤時間や勤務日数を減らして年収が壁を越えないように調整することを「働き控え」といい、企業の人手不足に繋がっていると問題になっています。
全都道府県で最低賃金がアップしていますが、この賃金アップに伴い働き控えをする人も増えてしまいます。
なぜ働き控えをするかというと、年収が上がったのに手取り金額が減ってしまう「働き損」と言われる状態を避けようとする人が多いからです。
年収の壁をこえたときの働き損がいくらくらいの金額になるのかを計算してみました。
壁を超えることで一番負担が大きいのは、社会保険料(106万円の壁)です。
わかりやすく表にすると以下のようになります。(あくまでも概算なので目安として見てください。)
| 年収 | ~103万円 | 104万円 | 105万円 | 106万円 | 107万円 | 108万円 |
| 所得税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 社会保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | 約15.3万円 | 約15.4万円 | 約15.5万円 |
| 手取り金額 | 約103万円 | 約104万円 | 約105万円 | 約90万円 | 約91万円 | 約92万円 |
年収106万円をこえたところで、手取りの逆転現象が起きていることがわかります。
働き損を防ぐためには、計算上では、106万円の壁にぶつかる人は年収を105万円以下におさえるか、それをこえてしまったら125万円以上になるように働くことが必要です。
※計算上、年収105万円の人と年収125万円の人に手取りの差はほぼないということになります。
130万円の壁にあたって配偶者の扶養を外れ手取りが減ってしまうのが嫌だという人は、年収153万円以上まで働くと社会保険保障もついた上に手取りも増えることになります。
ただ、ひとつ言えることは、年収の壁にあたって手取り金額が減ってしまったとしても、それは決して「働き損」ではありません。
社会保険に加入することで、「将来受け取る年金が増える」「傷病手当金や出産手当金がもらえる(健康保険に自分で加入している人が対象。被扶養者は対象外。)」等のメリットがあることを忘れてはなりませんね。