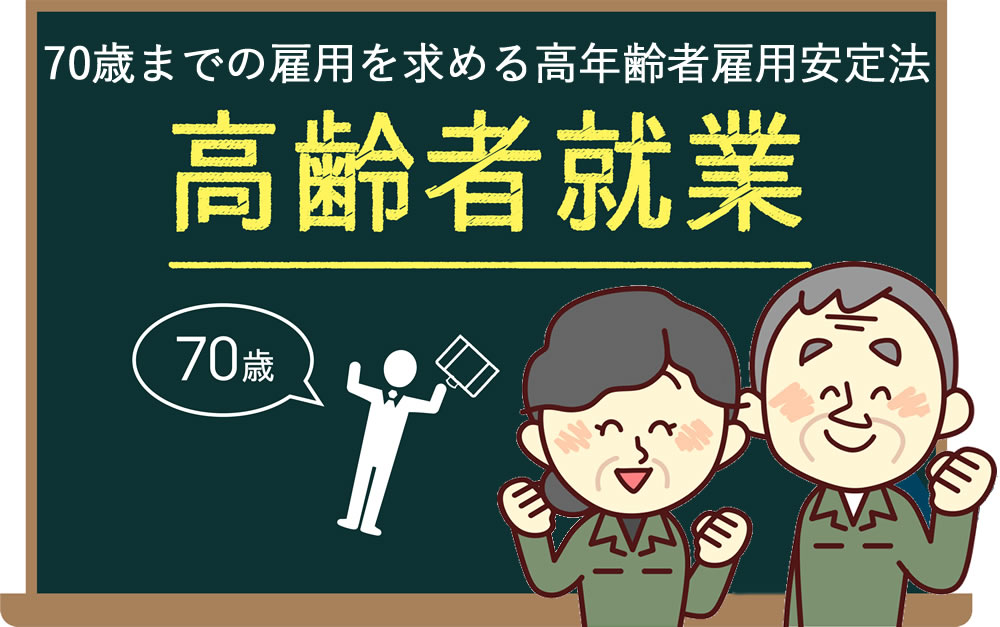
少子高齢化・人口減少が進む中でも経済活力を維持するため、働きたい高齢者が働き続けることができる環境整備をすすめるべく高年齢者雇用安定法の一部が改正され、令和3年(2021年)4月1日より施行されます。
この記事を読めば、改正高年齢者雇用安定法の概要と、企業はどう対応したら良いのかがわかります。
70歳までの雇用の努力義務とは具体的にどうしたら良いのか?罰則はあるのか?などについてもまとめます。
目次
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法について
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法は、正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」という。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律である。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律である。
働きたい高齢者が働き続けることができる環境整備のため、高年齢者雇用安定法の一部が改正されました。
これは、従業員が70歳になるまで就業機会を確保するように企業に求める改正法であり、令和3年(2021年)4月1日より施行されます。
改正前後のポイントをまとめます。
これまでの高年齢者雇用安定法のポイント
65歳までの雇用確保が義務です。
- 60歳未満の定年禁止
定年を定める場合は、60歳以上でなければなりません - 65歳までの雇用確保
65歳未満を定年にしている場合、下記のどれかの措置をしなければなりません- 65歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)
fa-check-circleCHECK
定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度のことです。
改正高年齢者雇用安定法のポイント
70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。
これまでの65歳までの雇用確保の義務に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、下記のどれかの措置を行う努力義務が課されます。
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
(a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
(b)事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行う社会貢献事業
fa-check-circlePOINT
この改正は、定年を70歳へ引上げることを義務付けるものではありません。
あくまでも、70歳まで働き続ける機会を確保するための努力義務となっています。
高年齢者雇用安定法に罰則はあるのか?
改正法による高年齢者雇用確保措置に関しては、罰則規定のない努力義務となっています。
違反した場合は指導、助言及び勧告はなされますが、罰則や違反企業の公表制度等はないようです。
まとめ
定年の年齢については、2025年4月から65歳定年制が全ての企業の義務となります。
改正高年齢者雇用安定法は、現段階では70歳までの雇用機会確保の努力義務ですが、今後は70歳定年が義務化される流れになっていくと言われています。
少子高齢化や人手不足は今度も加速していきます。労働者確保の観点からも、将来的なことも考えて高齢者雇用や定年制度について検討をしていく必要がありそうです。
この記事は、厚生労働省のホームページの内容をもとにまとめました。(外部サイトへ移動します)
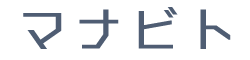
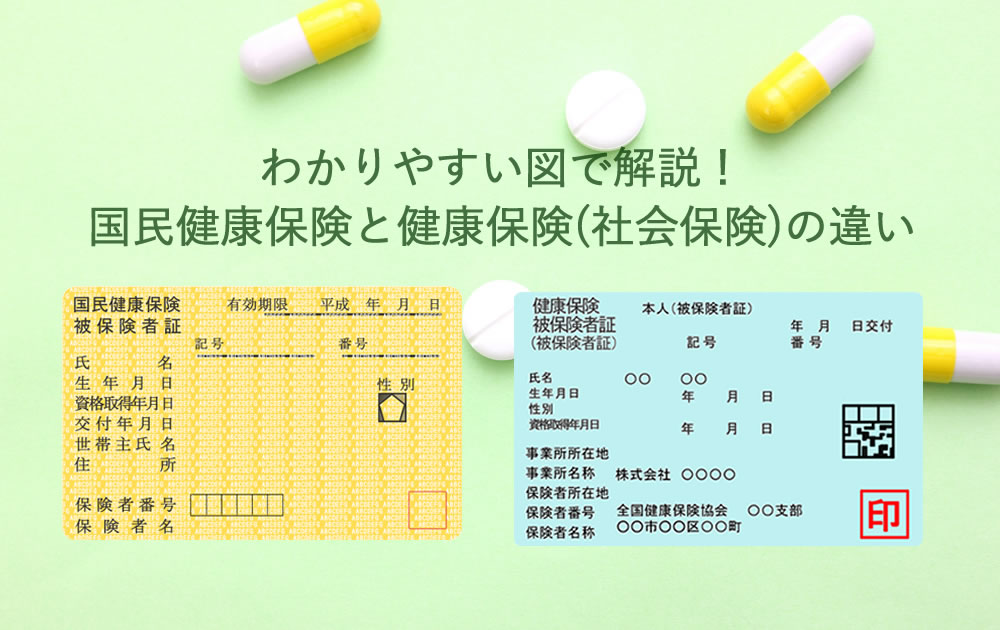

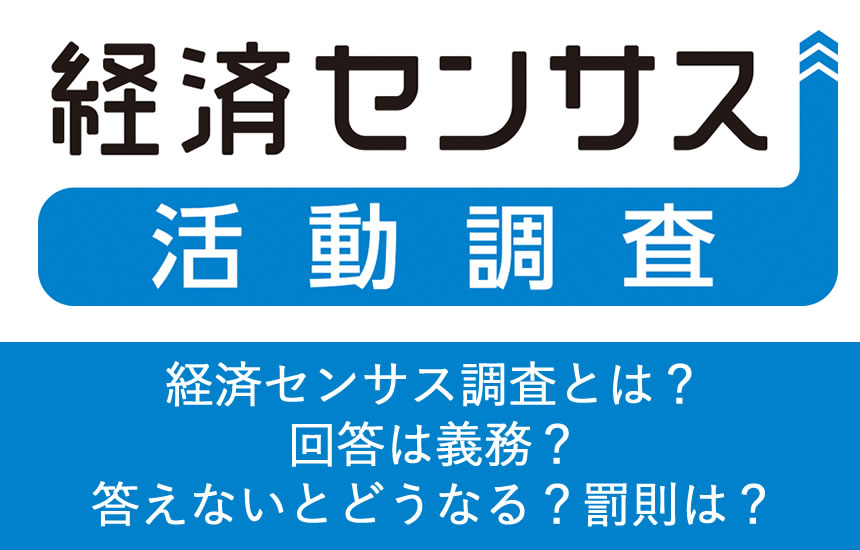




![[出生後休業支援給付金]育休中も手取り10割?!2025年4月スタート](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2025/04/ikukyu-syusshogoshienkyufu-150x150.jpg)




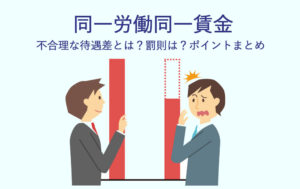

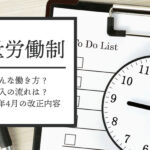

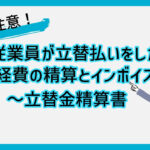

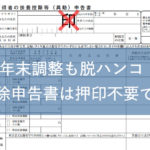

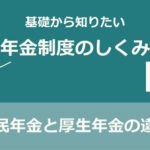
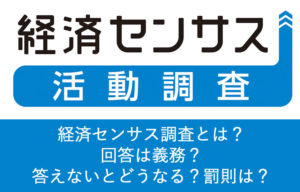



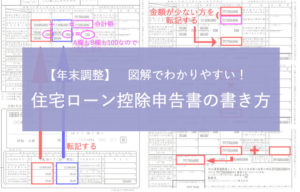

![電卓の[M+][M-][MR][MC]って何?メモリー機能を使いこなそう!](https://worker-training.com/manabito/wp-content/uploads/2022/05/dentaku-memorytop-300x169.jpg)