

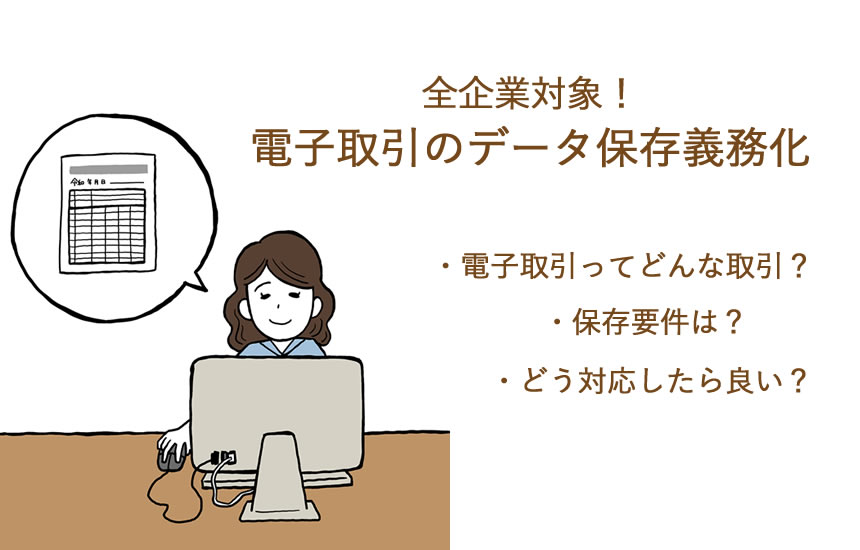
令和4年(2022年)1月から電子取引のデータ保存が義務化されました。
どういうことかというと、メール添付やダウンロード等で 電子的に受け取った請求書や領収証等は、紙の状態ではなくデータのまま電子保存しなければなりません。
「うちの会社は電子帳簿保存法に対応してないから関係ない」と思っていませんか?
この電子取引データ保存義務化は、すべての会社・事業者が対象です!
この記事では、電子帳簿保存法の改正による電子取引のデータ保存義務化に関するポイントをわかりやすくまとめています。
電子取引とはどんな取引のことか?電子取引データの保存要件は?外部システムを使わないで保存するならどう対応すればよいの?等について知ることができます。
目次
2022年(令和4年)1月1日より、電子取引の電子保存(紙ではなく、データのままで保存すること)が義務化されました。
令和4年度税制改正大綱にて、電子取引による取引情報の電子保存義務化について2年間の猶予期間が設けられることとなりました。
これにより、2023年(令和5年)12月31日までの2年間は、要件をみたせば経過措置として電子取引を紙で保存することができます。
その要件とは、「やむを得ない事情があると認められること」かつ「質問検査権に基づく書面の提示の求めに応じられるよう適切に保存がされていること」です。
2024年(令和6年)1月からは、すべての企業で電子取引の電子保存義務化スタートとなります。
電子取引のデータ保存義務化は、電子帳簿保存法に対応しているか否かに関わらず、電子取引をしているすべての企業が対象になります。
電子取引とは、国税庁によると「取引情報(*)の授受を電磁的方式により行う取引」のことだそうです。
(*)取引情報とは、取引に関する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項のことです。
具体的には、EDI取引、インターネットによる取引、電子メールで取引情報を授受する取引(添付ファイル含)、インターネットサイトを通じた取引等が電子取引にあたります。
わかりやすく身近な例で言うと、アマゾンや楽天市場などネットでのお買い物も電子取引にあたります。
これまでは、これらの電子取引データを書面で出力(紙に印刷)して保存することが認められていましたが、改正後は紙での保存が認められなくなりました。
電子取引をしたら、所定の方法によって取引情報のデータ保存をしなければなりません。
気になるPOINT
電子的に受け取った請求書や領収書等は、データのまま保存しなければなりませんが、真実性や可視性確保のための保存条件を満たしていなければなりません。
事後的な確認のために、検索できるような状態で保存することと、パソコン等を備えてすぐに出力できるようにしておくことが必要です。
次のいずれかの措置を行うことが必要です。
保存要件に対応した保存を行うにはどうすれば良いのか、具体例を2つあげます。
会計ソフトやクラウドサービスを利用せずに電子取引のデータ保存を行う方法もあります。
ここでは、要件を満たした保存方法として国税庁が示している保存の仕方を一例として紹介します。
ファイル名を規則性をもった内容にする または エクセルで等で索引簿を作成する
「取引先」や「年月日」など規則性のあるフォルダに格納して保存する
事務処理規程を作成して備え付ける
詳細を説明していきます。
規則性のあるファイル名とは、電子取引データのファイル名に 日付・取引先名・金額などを明記することです。
例)
2022年1月10日に、(株)国税社から請求書(100,000円)をPDFで受け取った場合のファイル名
・ 20220110_国税社_100000.pdf
電子取引データのファイル名を連番の番号にして保存し、Excel等の表計算ソフトで索引簿をつくる方法でもOKです。
索引簿を使って、データファイルを検索することができるようにします。
索引簿のサンプルは、国税庁のホームページからダウンロードできます。
電子取引データのファイルを、「取引先」や「年月日」で区切ってまとめたフォルダに格納して保存します。
どのフォルダに何のデータファイルが保存されているかがわかるように保存することが重要です。
例)
20220110_国税社_100000.pdf の保存先
↓
・(株)国税社フォルダ
または
・2022年1月フォルダ など
タイムスタンプ付与や電子帳簿保存法に対応したシステムやクラウドサービスを利用しない場合、または現在利用している会計ソフトが電子取引データ保存の要件を満たしていない場合等は、真実性の確保のために電子取引データの訂正・削除の防止に関する事務処理規程を策定することが必要です。
事務処理規定の雛形は国税庁から提示されていて、Word文書をダウンロードすることもできます。
電子取引のデータ保存要件を満たしていない場合罰則があるのかについてですが、国税庁の解説(一部抜粋)は以下の通りです。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録について要件を満たさず保存している場合や、その電磁的記録の保存に代えて書面出力を行っていた場合には、保存すべき電磁的記録の保存がなかったものとして、青色申告の承認の取消の対象となり得ますので注意してください。
・・・
なお、青色申告の承認の取消しについては、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。
・・・
申告内容の適正性については、税務調査において納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
青色申告取り消しについて示唆されていますが、後に「その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。」という補足説明がなされています。
しかし、電子取引の電子保存が義務であることには変わりないので、企業としては対応が必要となります。
経過措置によって2023年(令和5年)12月31日までの2年間は猶予されることとなりましたが、今からしっかりと準備をしておきたいところです。
令和5年度税制改正大綱により、電子帳簿保存法の要件が一部緩和されました。令和5年度税制改正における電子帳簿保存法に関する内容は、下記の記事で解説しています。