

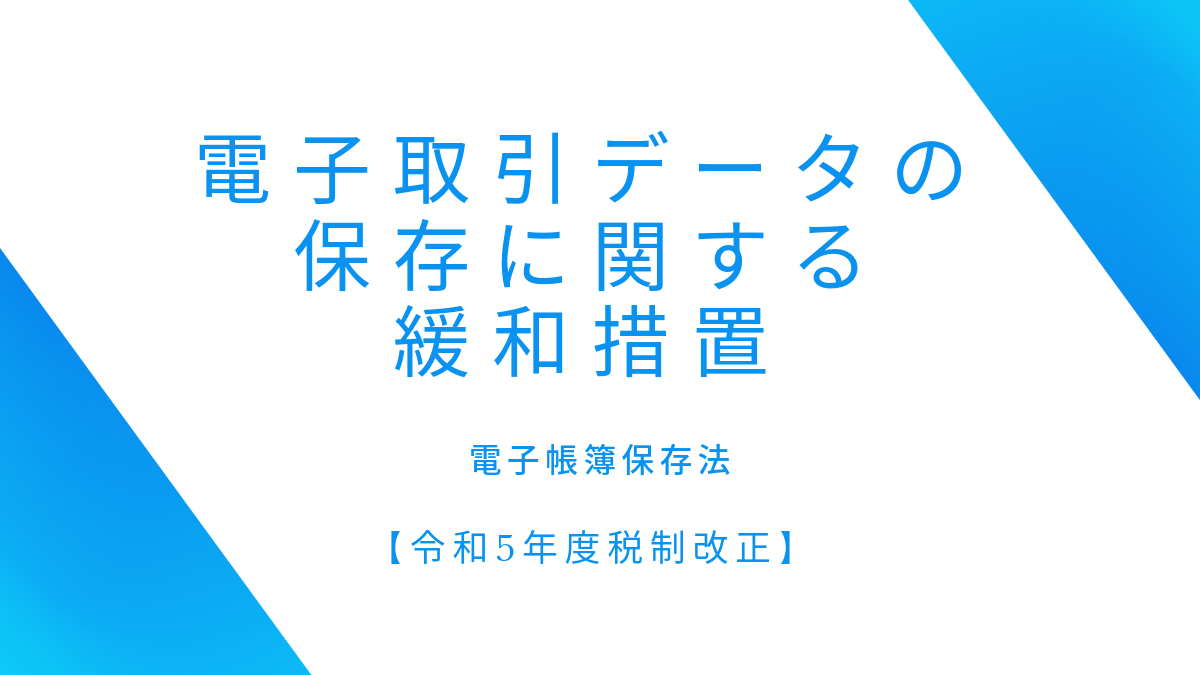
令和5年度税制改正大綱により、電子帳簿保存法の要件が一部緩和されました。
この記事では、令和5年度税制改正における電子帳簿保存法に関する内容を解説します。
特に「義務化」という点で多くの方が気になっているであろう「電子データ保存義務化」についてクローズアップしてお届けします。
目次
電子帳簿保存法とは、以下のことを定めた法律です。
電子帳簿保存法の概要や、2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法に関する詳細は、こちらの記事にまとめています。
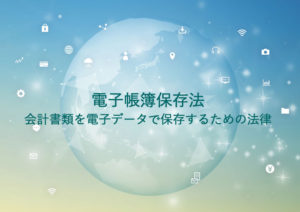

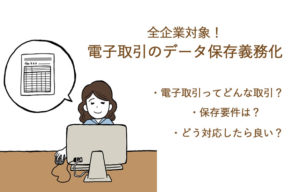
電子帳簿保存法の保存要件は3つに区分できます。
| ① 電子帳簿等保存 | ② スキャナ保存 | ③ 電子取引データの保存 |
|---|---|---|
| パソコン等を使用して作成した帳簿や取引書類を電子で保存し、紙保存を不要とする | 取引相手から紙で受け取った書類等を画像データ化して保存し、紙の保存を不要とする | メールやWEB上でやり取りした電子ファイルをデータで保存することを義務化 |
| 改正のポイント2022年より要件が緩和され、事前承認が不要となりました。 | 改正のポイント2024年1月以降多くの企業で保存要件が緩和されます。 | |
令和5年税制改正における電子帳簿保存法に関する内容は下記の4つです。
それぞれ解説していきます。
電子取引のデータ保存義務化については、令和4年度改正において、令和5年12月31日までの2年間の経過措置が設けられました。
この措置の内容とは、下記の2つを条件として、紙での保存を可能とするものでした。
この猶予措置は、適用期限(2023年12月31日)をもって廃止されます。
令和5年の改正では、条件付きで検索機能の確保の要件等を不要とする新たな猶予措置が設けられます。次の②で詳しく解説します。
電子取引データの保存要件のうち、検索機能の確保の要件(以下、検索要件と言います)が不要となります。
検索要件のすべてが不要となる対象者は次のいずれかを満たす者です。
今回の改正によって「データを出力した書面の提示・提出」が可能であれば、どんな企業でも検索要件が免除されるということになります。(※検索要件が免除されるだけなので、電子データの保存自体は必要です。)
いままで電子取引データを印刷した紙をファイリングしていた場合で、電子帳簿保存用のシステム導入が難しい場合でも、下記を満たす保存をしていればOKです!
※令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用されます。
検索要件の他、電子取引のデータの保存要件については下記の記事で詳しく解説しています。
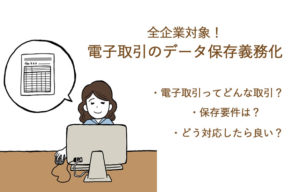
スキャナ保存で求められる要件の一部が不要となりました。
スキャナ保存制度とは、決算関係書類を除く国税関係書類を、一定の要件の下でスキャナによるデータ保存をすることで、紙の書類の保存が不要になるというものです。
緩和されるのは以下の内容です。
スキャナ保存に関してはどんどん要件が緩和されていっているため、導入のハードルが下がり利用しやすい環境になってきていると言えます。
※令和6年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類について適用されます。
国税関係帳簿に関して申告漏れがあった場合、過少申告加算税が課されますが、一定の要件を満たす「優良電子帳簿」については、過小申告加算税が5%軽減されます。
令和5年税制改正では、軽減措置に関する対象帳簿の範囲が明確化されました。
帳簿の具体例は次の通りです。
※令和6年1月1日以後に法定申告期限などが到来する国税について適用されます。
令和5年度税制改正による電子帳簿保存制度の内容についてもっと詳しく知りたい方は、国税庁が発行している下記のパンフレットが参考になります。