

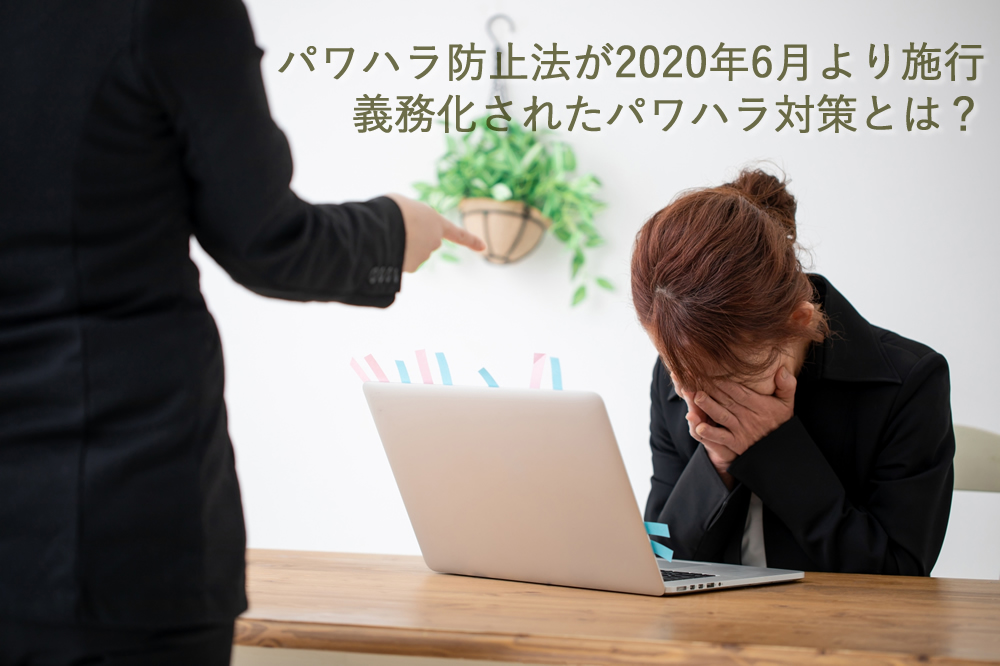
2020年6月より、パワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律(以降、パワハラ防止法と記します)が施行され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。
中小事業主の場合は現時点では努力義務ですが、2022年4月1日から義務化されます。
パワハラという言葉をよく耳にするようになって数年たちますが、パワハラと教育・指導との線引きはどうなっているのでしょう?
パワハラ防止法の概要についてまとめます。
目次
パワハラとは、パワーハラスメント(Power Harassment)の略称。
パワーハラスメントとは、立場や権力の優位性を利用した、主に社会的な地位の強い者による、自らの権力や立場を利用した不当な要求や嫌がらせ、苦痛を与える行為のことです。
2019年6月5日、改正労働施策総合推進法が公布され、2020年6月より施行されました。
これにより、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止となります。
適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
職場におけるパワハラとは、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。
※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません
パワハラとなりえる代表的な言動について、6つの行為類型があります。
厚生労働省HPにあるリーフレットに具体例が記載されています。
> 2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます![PDF:733KB]
「パワハラ防止法」における事業主の義務について詳しくみていきます。
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されます。
事業主がパワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を怠った場合には、パワハラ防止措置の実施状況について指導や勧告の対象となります。
これに従わなかった場合、その旨が公表されることがあります。(改正労働施策総合推進法第33条1、2項)
厚生労働大臣はパワハラ防止措置の実施状況について事業主に報告を求めることができ(同法第36条1項)、事業主がその報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料が課される可能性があります(同法第41条)。
この記事は、厚生労働省のページを参考にして書きました。