

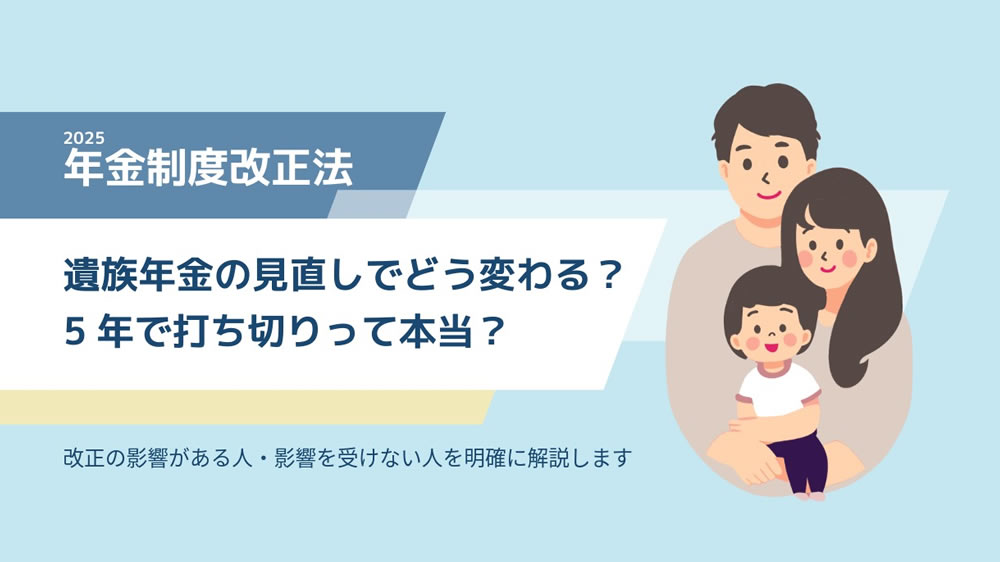
「遺族年金制度が改悪」「5年で打ち切られる」などというワードで炎上していることはご存知でしょうか?
遺族年金の改正についてきちんと調べてみると、決してすべてが「改悪」とは言い切れない変更点があることがわかりました。
炎上しているワードに惑わされることなく、改正内容を正確に知っておくことが大切です。
この記事では、2025年の年金制度改正法で遺族年金制度がどのように変わったのかをまとめます。改正の影響がある人・影響を受けない人を明確にして解説していきます。
目次
遺族年金制度は、亡くなった人の遺族の生活を支えるための制度で、遺族年金は、亡くなった人が保険料納付などの要件を満たしていればその遺族が受け取ることができる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の加入状況によって、どちらか、または両方が支給されます。
遺族基礎年金は、国民年金や厚生年金の被保険者だった人が亡くなった場合に、受給要件を満たしていれば、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
・子とは、18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の人です
・婚姻していない場合に限ります
・死亡当時胎児の子は生まれたあとに対象になります
厚生年金の被保険者だった人が亡くなった場合に、受給要件を満たしていれば、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が遺族厚生年金を受け取ることができます。
一般的に、会社員(第2号被保険者)は国民年金と厚生年金保険に加入しているので、亡くなったときに妻と子ども(遺族)がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえます。(納付要件等あり)
遺族基礎年金については、子どもが受け取りやすくなるように改正されます(2028年4月から実施)
これまでは、遺族基礎年金を受けとれない父母と生計を生計を同じくしている場合、子どもへの遺族基礎年金の支給もされず、死別後の再婚や親の収入、養育者との関係などによって、子どもが年金をうけとれないケースがありました。
たとえば、元夫の死後、妻が遺族基礎年金を受給していても、妻が他の人と再婚すると妻は遺族年金を受け取れなくなります。このようなケースでは、子どもが母と生計を同じくしていると子どもへの支給も停止されていましたが、改正後は親が再婚しても子どもは遺族基礎年金を受け取ることができるようになります。
死亡前に親が離婚していて、子を養育していた方の親が死亡した場合に、死亡後にもう一方の親に引き取られた場合でも、子どもは遺族基礎年金を受け取れるようになります。
親の収入要件超え(年収850万円以上)によって子どもが遺族基礎年金を受けとれない、ということもなくなります。
祖父母などの直系血族の養子となった場合も、子どもは遺族基礎年金を受け取れるようになります。
このように、多様な家庭環境にあっても、子どもの生活の安定のため、子どもは年金を受け取ることができるようになります。
また、遺族基礎年金の子の加算額も増額(年間約23.5万円→年間約28万円へアップ)されるため、子どもを育てる家族が子どものために受け取る年金が増え、生活の安定につながるようになります。
ここからは、遺族厚生年金の改正内容について確認していきます。
今回の改正の趣旨は「男女差を解消すること」です。
2025年の年金制度改正法で主に大きく見直されたのは、「遺族厚生年金」です。
改正前の仕組みでは、男女によって受給できる年齢や期間に大きな差がありましたが、今回の改正により男女差が解消され、男女共通となりました。
詳しい改正点は以下の通りです。
※60歳以上で死別した場合は無期給付となります。(これは現行のまま変更ありません)
遺族厚生年金の改正点の詳細について解説していきます。
子どもがおらず60歳未満で死別した場合、原則5年間の有期給付となります。
有期給付の額は、新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現行の遺族厚生年金額の約1.3倍となります。
5年間の有期給付の終了後も、障害や、収入が不十分でない等で配慮が必要な場合は、5年目以降も給付を継続して受け取れます。(継続給付)
改正前の遺族厚生年金制度では、女性は死別時の年齢によって有期給付/無期給付が分かれ、男性は55歳以上で死別した場合に限り60歳から無期給付されるという明らかな男女差がありました。
今回の改正では、男女関係なく支給要件が統一されます。
これまで、遺族厚生年金の受給には年収850万円未満という収入要件がありましたが、今回の改正でこの要件が撤廃され、年収に関係なく受け取れるようになります。
専業主婦が多く「夫が妻を養うのが主流」の時代から、現代の「共働きが主流」の時代に変わったことで、遺族年金制度も時代背景に合わせて見直されたということですね。
法律では、遺族年金の見直しは2028年4月施行予定となっていますが、女性に関しては2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。(既存受給者との整合性確保のため)
今回の見直しで影響を受ける人について整理すると、以下のようになります。
女性の場合
18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の人(=施行後に原則5年間の有期給付の対象となります)
改正前は、子がいない妻は、夫と死別したときに30歳未満なら5年間の有期給付、30歳以上なら無期給付をうけられ、しかも40歳から65歳未満に受給権を得ると中高齢寡婦加算がついて増額となっていました。
これが、子どもがおらず60歳未満で死別したときは、原則5年の有期給付に変更となります。
中高齢寡婦加算の金額も徐々に縮小されます。
男性の場合
18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の人(=新たに5年間の有期給付を受けられるようになります)
改正前、夫は妻と死別したときに55歳以上でなければ受給権はなく、しかも55歳以上だったとしても実際に給付されるのは60歳からという、なんとも女性との不平等が大きい制度設計でしたが、改正後は年齢も性別も関係なく、同じ条件で給付を受けられるように変わります。
下記に該当する人は、今回の見直しによる影響はありません。
「女性にとって改悪すぎる」という声も多いようですが、実は平成元年4月2日以後生まれの世代が対象で、昭和生まれの女性は影響をうけないんだね。
18歳未満の子ども(18歳年度末まで)がいる場合は、こどもが18歳の年度末を迎えるまでは給付内容が現行制度と変わりなく、見直しの影響はありません。
ただし、子どもが18歳の年度末を過ぎると、5年間の有期給付となります。(有期給付加算対象。その後の継続給付も対象です。)
子のいない配偶者への遺族厚生年金は原則「5年間の有期給付」となります。(※5年経過後も年収が少ないなど、配慮が必要とされる場合は延長されます)
子どものいない妻にとっては、30歳以上で夫と死別したときにこれまでの「一生給付」から「5年間の有期給付」に変わるため、受け取れる遺族年金の総額は大幅に減少することになります。(※子どもがいない30歳未満の女性は、改正前から5年間の有期給付だったので変更ありません)
遺族年金が夫亡き後の生活を生涯保障してくれるわけではなく、一時的な自立支援に変わるようなイメージですね。
改正前は、男性は55歳未満で妻を亡くしても遺族年金が一切もらえませんでしたが、改正後は男女関係なく遺族年金を受け取れるようになり、男性にとって不平等だった問題が解消されます。
働く妻を亡くした夫にとっては改良(いままで受け取れなかった年金が受け取れる)で、働く夫を亡くした妻にとっては改悪(受け取れる年金が減る)とも言えるね。
現代の多様な家庭のあり方や働き方の変化に応じて、遺族年金制度が改正されます。
受給資格や受給額については、複雑でわかりにくいので「よくわからないけど別にいいや」と思ってしまいがちですが、いざという時に頼りになるのが遺族年金です。
いざ「その時」がきたときに慌てないためにも、2028年4月の施行の前に、自分が改正の影響を受けるのか等をしっかりと理解しておくことが大切です。
遺族年金制度の改正をきっかけに、民間保険の加入や見直し、貯蓄設計など、家族に何かがあったときの備えについて考えてみることが、将来の安心につながりますね。